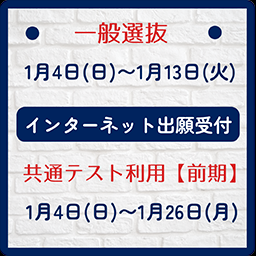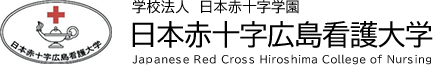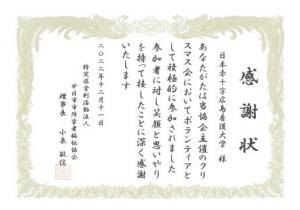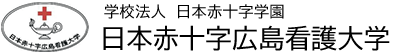本文
学生ボランティアの活動内容
学生ボランティア活動の推進
ヒューマンケアリングセンターでは、令和4(2022)年度から、学生ボランティアの総合窓口として学外のニーズと学生のマッチングを組織的に行うことを目的に活動を開始しています。
主に廿日市市や、市内の団体と連携し、ボランティア募集の告知を行い、活動用のユニフォームを支給するなど学生の活動をバックアップしています。募集の方法は、内容に応じて、学内でとりまとめて団体等への申し込みを実施できるよう、学生からの応募用入力フォームや学内での募集サイトを作成するなど工夫することで、学生の応募の反応が早まり、応募数が増加しています。
参加した学生は、ボランティア活動参加後に学びや気づきなどをヒューマンケアリングセンターに報告しています。
本学の学生ボランティアはこんな活動をしています。
みんなでクリスマスケーキを作りました。
2023年12月25日に廿日市市串戸市民センターで行われた、小学生対象の「冬休みケーキデコレーション教室」の補助スタッフとして学生6人が参加しました。
当日は、小学生がひとり1ホールのケーキスポンジに生クリームとフルーツをデコレーションしクリスマスケーキを完成させ、自宅に持ち帰るという参加した小学生だけでなくボランティアの学生もワクワクするようなイベントでした。



四季が丘小学校防災キャンプにボランティアとして参加してきました。
本学は、毎年四季が丘小学校で行われる防災学習イベントにボランティアで参加しています。今年も9月30日(土)に、学生6人、教員1人が参加し、応急救護のブースを担当しました。
学生は、入学直後に学んだ「赤十字救急法」を思い出しながら、三角巾を用いた応急手当について「どうやったら伝わるだろう?」と工夫しながら、身振り手振りを加えて子ども達の実技のお手伝いをしていました。
本学の1年生は、今月から小学校実習が始まりますが、ボランティア活動を通して、多様な世代の人々とコミュニケーションをとり交流することが、実習での対象理解に役立っています。

障害者との交流クリスマス会
令和4年12月障がい者の交流会としてステージ発表などが行われるクリスマス会に参加し、その積極的な活動から本学学生に対し感謝状を授与されました。学生は障害のある方に合った関わり方などを学ぶことができました。
「あいプラザまつり」
令和4年11月6日、廿日市市主催のまつりが3年ぶりに開催され、医師会をはじめ18団体が健康に関するブースを出展し、学生はブースの補助や受付などを担当しました。学生は、健康のことだけではなく、育児相談、歯科相談、子供から大人まで誰もが楽しめるようなニュースポーツといった様々な企画があり運営側から地域の方々と触れ合えたので楽しみながら参加できたようです。
100万羽おりづるプロジェクト ボランティア参加
令和4年9月24日、日本赤十字社広島県支部が主催された青少年赤十字創設100周年特別事業「100万羽おりづるプロジェクト」、ひもで連結した579,658羽のおりづるは長さ15.5797キロメートルとなり、見事、ギネス世界記録(ギネスワールドレコーズ)に認定されました。
今年1月から実施されたプロジェクトに県内の多くの学校や施設が参加し、集まったおりづるは120万羽もあったとのことです。
本学では、学生と教職員が6月からおりづるの作成に協力しました。8月に延べ34人の学生が、集まったおりづるを一日で1万羽以上連結させ、9月22日~24日に行われたイベント当日は、6人の学生が参加しました。
参加した学生からは、「ひとりの力は小さいがたくさんの力が集まると大きなものになることを実感した」「平和を願って多くの方が折られたつるを連結する作業は、自分自身が平和を願っていることを発信する一つの行動となった」「自分自身は1日しかボランティアに参加できなかったが、陰で頑張ってくださっている方の存在に気づくことができた」など今後のボランティア活動の意欲にもつながったようです。


骨髄バンク推進全国大会2022in広島 社会を変えるアイデアフェス~想像力が、いのちを救う。~ 準グランプリ受賞
令和4年9月23日、日頃から骨髄バンクのドナー登録説明員を行っている4年生の学生が、ワークショップで他大学の学生と共に骨髄バンクの登録者を増やすための取り組みについて考えを出し合い、1つのアイデアにまとめ、そのアイデアを骨髄バンク全国大会でプレゼンしました。
発表した内容は、準グランプリを受賞し、ポスター化されました。
骨髄バンクのドナー登録説明のボランティアは、下級生に引き継がれています。
廿日市市議会議員との意見交換会
令和4年6月29日、学生8名が廿日市市議会議員と意見を交わしました。
参加前は「選挙権を持つ歳になったが政治への関心の持ち方がわからない」「どんな仕事をされているのかよくわからない」など不安な様子でしたが、1時間程度の意見交換の後は、「議員を身近な存在として感じることができた」、「思ったより堅苦しくなかった」など気持ちが和らぎ、参加した学生全員が選挙に行こうと意識に変化があったようです。

阿品台ウォーキング&宝探し ボランティア参加
令和4年6月26日、学生2名が「阿品台ウォーキング☆宝探し」のイベントにおいて、地域の参加者の血圧測定などの健康チェックのボランティアを実施しました。
2.5㎞のコースを参加者と一緒にウォーキングする途中では、参加者の体調を伺うなど阿品台の地域住民との交流を深めることができました。