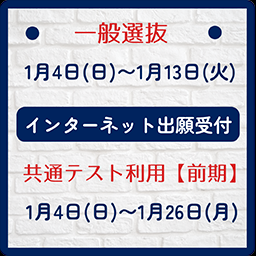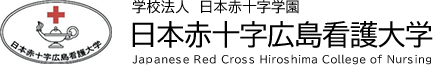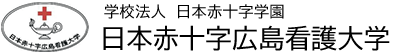本文
認知症サポーター養成講座を開催しました
「認知症サポーター」養成講座
地域において認知症の方と家族が必要としている支援をできる範囲で行う応援者として活動できるよう、地域の方及び学生を対象に「認知症サポーター養成講座」を開催しています。
内容 1.認知症サポーター養成講座とは
2.原因疾患別の行動・心理状態の特徴
3.認知症になりにくい生活
4.認知症の人の「内的世界」を理解する事例演習
令和7年度講演会実施のご報告
令和7年10月1日(水)に社会福祉協議会の共催により「認知症サポーター養成講座」を開催しました。
今年度も広島県認知症介護指導者の田中薫氏を講師にお招きし、1年生139名が参加しました。
この講座の目的から始まり、原因疾病別の行動・心理症状の特徴や認知症になりにくい生活をご紹介いただきました。後半の事例演習では、認知症の人の内的世界を理解することを学びました。
参加した学生からは「認知症に対する考え方が変わりました」「認知症について若いうちから知っておくと、寄り添える人が増えると思う」「これからの実習で高齢の人と関わる時に参考にしたい」「看護師になると認知症の方と接することが多くあるのでとても為になりました」と、将来の専門職としての活動に直結する学びを得たとの感想が寄せられました。
ヒューマンケアリングセンターでは、学生が、看護職としてだけでなく、地域住民としても、ふだんから認知症の人への支援を行い、地域の機関と協力して暮らしやすいまちづくりに参画する意識が高まる学修支援を行っています。
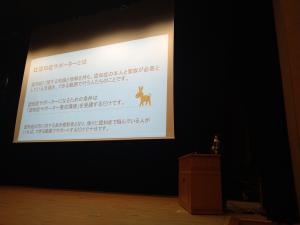
令和6年度講演会実施のご報告
令和6年10月2日(水)に社会福祉協議会と廿日市市地域包括支援センターとの共催で「認知症サポーター養成講座」を行いました。
認知症サポーターとは、地域で認知症の人やその家族にできる吐手で手助けをする地域の応援者です。キャラバンメイトの田中薫氏にお越しいただき、1年生の131人、地域の方々が参加しました。
認知症の人の症状、予防方法、「内的世界」を理解する講義・演習を行い、講座と通して、学生からは、「認知症に対する認識が大きく変わった」「思いや言動を理解し、関わっていくことがわかった」「認知症の人との接し方を兄弟や友達に教えたい」という感想が聞かれ、認知症の方を理解するきっかけとなりました。
また、地域包括支援センターでの「もの忘れ相談会」も同時開催していただきました。


令和5年度講演会実施のご報告
令和5年9月27日(水)に社会福祉協議会との共催で「認知症サポーター養成講座」を開催しました。
今年度は1・2年生190人が参加し、事例をもとに認知症の方の「内的世界」を理解する講義・演習を行いました。広島県認知症介護指導者の田中薫氏による具体的な事例を用いた内容に、参加した学生からは「認知症に対するイメージが変わった。」「私たちが正しくサポートすることが必要だと思った。」「認知症の方を否定するのではなく、認知症の方の世界に入り込んで接することが大切ということを学んだ。」など感想が寄せられました。
研修会を通して認知症に対する理解が深まり、看護職としてだけではなく住民としても認知症の方に積極的に関わり、思いを理解し、見守り・サポートすることの大切さを学ぶことが出来ました。




令和4年度講演会実施のご報告
令和5年1月30日(月)「認知症サポーター養成講座」を開催しました。
廿日市市認知症サポーターの田中薫氏による講義は、具体的な事例を用いてお話しされ、認知症の人をより身近に感じることができました。また、演習では、認知症の人の立場になり、様々なシチュエーションで認知症の人がどのように考えているのか「内的世界」を理解した上、私たちがどのように接したら良いかを学びました。
参加者からは、受講する前と受講した後では認知症の人に対するイメージが変わり、「認知症の方々が感じている気持ちを理解し汲み取り寄り添っていきたい」、「まず声をかけてみようと思う」、「目線をあわせて優しい語り口調で話しかけることからはじめてみたい」「介護、福祉、介護者のご家族の声をもっと聴きたい」等意見が寄せられました。
看護職として必要な知識であるため、今後も学生に講座の意義を周知し、学生の学ぶ機会を提供していきたいと思います。
令和3年度講演会実施のご報告
令和4年1月17日(月)、「認知症サポーター養成講座」を開催しました。
今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ハイブリット形式(対面とオンラインの併用)で行い、約70名の学生や教職員が受講しました。
講義では、講師の廿日市市認知症サポーターの田中薫氏が、具体的な事例を用いてお話しされ、認知症の人をより身近に感じることができました。また、演習では、認知症の人の立場になり、様々なシチュエーションで認知症の人がどのように考えているのか「内的世界」を理解した上、私たちがどのように接したら良いかを学びました。
参加者からは、「認知症と一概に言ってもいろいろ種類があり、ひとまとめにはできないと思った。」「1人の人としてきちんとケアをしていかなければいけないなと思った。」「困っている様子の高齢者の方がいたら、様子を見て声をかけてみるようにする。」「認知症を理解できる人を増やしていく」など、意欲的な意見も聞かれました。
看護職として必要な知識であるため、今後お学生に講座の意義を周知し、関心を深める支援をしていきます。