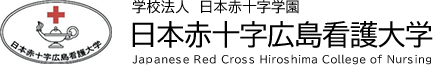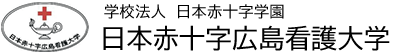1 本ガイドラインの目的
本ガイドラインは、教職員が業務や研究活動で生成AIを利用する際の注意事項を定めたものです。生成AIは、業務効率の向上や新しいアイデアの創出に役立つ一方で、不適切な利用によって法令違反や権利侵害のリスクが生じる可能性があります。本ガイドラインの遵守を通じて、生成AIの適切な利活用を促進し、教育・研究活動を支援することを目的とします。
なお、生成AI技術の進展や法制度、社会情勢の変化を踏まえ、本ガイドラインは必要に応じて見直しが行われる場合があります。
2 本ガイドラインが対象とする生成AI
本ガイドラインは、以下の開発元が開発した生成AIモデル、またはこれらのモデルをベースにカスタマイズされた生成AIモデルを利用するサービス(API連携を含む)を対象とします。該当しない生成AIモデルについては業務での利用を禁止します。
- Open AI
- Anthropic
- xAI
その他の生成AI及び生成AIを活用したサービスについては、社会情勢や技術の進展を踏まえ、随時検討します。
また、利用を希望する生成AI関連のサービスがある場合は、総務課までご連絡ください。
3 ガイドラインの適用範囲
本ガイドラインは、以下の状況に適用されます。
- 教職員が業務、教育、研究活動で生成AIを利用する場合
- 学内の機器やネットワークを使用して生成AIを利用する場合
- その他、本学の許可を得て生成AIを利用する場合
生成AIを利用する際は、利用条件や責任の所在を十分に理解し、適切に運用する必要があります。生成AIを用いた結果の責任は、まず利用者本人に帰属しますが、その行為が大学の業務として行われる場合には、最終的に大学に帰属することを十分に認識してください。
4 禁止される行為
以下の行為を禁止します。これらのルールは、法令や学内規程の遵守、および教育・研究活動の適切性を確保するために定められています。
(1)個人情報を生成AIに入力する行為
氏名、住所、連絡先、人物が特定される顔写真などの個人情報を生成AIに入力することは禁止です。入力データが外部のサーバーに保存され、学習に利用される可能性があるため、個人情報保護法に違反するリスクがあります。
(2)他者が著作権を有するデータを無断で利用する行為
他者が著作権を持つ文章や画像などのデータを無断でプロンプトに入力することは禁止です。特に、他者の著作物を基にした類似生成物を作成する目的の場合、著作権侵害となる可能性があります。
(3)商標権・意匠権を侵害する可能性がある行為
登録商標や意匠を含むデータを無断で入力することやそれに基づく生成物を利用することは禁止です。利用を検討する場合は、事前に十分な調査を行い、権利侵害のリスクを回避してください。
(4)機密情報を生成AIに入力する行為
学内の機密情報や秘密保持契約等により外部から得た情報を生成AIに入力することは禁止です。これらの情報が外部サーバーに保存されることで、意図せず情報が共有される可能性があります。
<機密情報とは>
大学が外部に公表していない情報のうち、情報が漏洩した場合に教職員又は学生の生命、財産、プライバシー等や大学の教育活動及び管理運営に重大な影響を及ぼすものを指します。
(具体例)
- 在学生、卒業生、教職員の個人情報(氏名、住所、成績、健康関連情報など)
- 非公表の入試問題および選考基準
- 内部でのみ共有される財務情報(予算計画、取引先との契約条件など)
- 学内のセキュリティ計画や体制図
- 未公開の研究データや特許申請前の研究成果 など
(5)虚偽または誤解を招く生成物の作成および使用
生成AIの出力には虚偽の情報や差別的な内容が含まれる場合があります。生成物を利用する際は、内容の正確性を確認し、不正確な情報の配布を避けてください。
(6)学生の成績評価や重要な判断を生成AIに依存する行為
成績評価や教育活動における重要な意思決定は、教職員の専門的判断に基づいて行うべきです。生成AIに依存した評価は行わないでください。
5 データ入力に際して注意すべき事項
生成AIを安全かつ適切に利用するため、以下の点に注意してください。
(1)入力するデータの目的を明確にする
生成AIを利用する際は、入力データが業務や研究の目的に適しているかを事前に確認してください。不要な情報や過剰な詳細情報は含めないようにしてください。
(2)個人情報や機密情報を特定可能な形で入力しない
データの匿名化や仮名化、一般化などの適切な手法を用い、特定の個人や組織を識別できないようにしてください。たとえば、個人名を「社員A」などの仮名に置き換えるほか、年齢や住所は範囲化(例:30代、東京都)することで特定性を排除します。また、必要に応じてランダム化やデータ合成を活用し、情報の秘匿性を確保してください。
(3)生成物の品質向上のためにプロンプトを工夫する
入力内容が曖昧だと不正確な生成物を得る可能性があります。また、生成AIには「ハルシネーション」と呼ばれる、実際には存在しない情報をもっともらしく生成する特性があります。明確で具体的なプロンプトを設計し、生成物の内容は必ず自分自身で十分な確認を行ってください。
(4)意図しないデータ流出を防ぐ
意図しないデータ流出を防ぐため、利用する生成AIのサービスが入力されたデータをどのように扱うかを確認してください。たとえば、入力データがAIの学習に使われない設定がある場合は、その設定を有効にしてください。利用する前には、サービスの利用規約やプライバシー設定を必ず確認してください。
6 生成物を利用するに際して注意すべき事項
生成AIによる生成物を利用する際には、以下の点に注意してください。
(1)生成物に虚偽や誤りが含まれる可能性
生成AIは、言語モデルの原理に基づき、もっともらしい文章を確率的に生成します。
そのため、生成物には虚偽の情報や誤りが含まれている場合があります。内容を盲信せず、必ずご自身によって根拠や裏付けを確認してください。
(2)権利侵害のリスク
生成物が意図せず他者の既存の権利を侵害する可能性があります。以下の点に特に注意してください。
- 著作権侵害
生成物が既存の著作物と同一または類似している場合、利用が著作権侵害に該当する可能性があります。特に、作家名や作品名を指定して生成しないでください。 - 商標権及び意匠権侵害
ロゴやキャッチコピー等を商用利用する場合、商標権や意匠権を侵害する可能性があります。事前調査を徹底してください。
(3)生成物に著作権が発生しない可能性
生成物には著作権が発生しない場合があり、法的保護が及ばない場合があります。生成物をそのまま利用せず、加筆・修正を加えることを推奨します。
(4)開発元の利用規約による制限の遵守
開発元の利用規約による制限を遵守してください。生成AIの利用規約を確認し、商用利用が許可されているか、生成したコンテンツであることの明示が必要かどうかなどを確認してください。