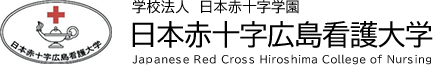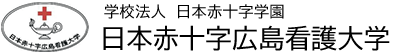本文
日本赤十字広島看護大学DX推進計画
令和7年4月29日
日本赤十字広島看護大学
1. 背景と目的
本学は、平成12年4月の開学以来、赤十字の人道の理念に基づき、「命と尊厳を守るヒューマンケアリングの実践者の育成」に努め、これまでに国内外の保健・医療・福祉の分野で幅広く活躍できる人材を輩出し、看護学の発展及び人類の福祉の向上に寄与してきました。
しかしながら、本学を取り巻く環境は、18歳人口の急激な減少、AI等の技術革新による教育市場の多様化やグローバル化、開学から25年を経過したことによる施設整備の必要性など、急速に変化しています。さらに、看護教育においては、高度化・複雑化する医療現場に対応できる人材育成や、地域包括ケアシステムの推進に伴う地域社会との連携強化など、新たな要請に応えるには、実践的な看護能力の育成が喫緊の課題となっています。
このような状況下で、本学が「命と尊厳を守るヒューマンケアリングの実践者の育成」という使命を継続して果たし、社会から必要とされる教育・研究機関であり続けるため、本学はデジタル化の急速な進展を教育、研究、社会貢献の全領域にわたって積極的に活用する絶好の機会と捉え、デジタルトランスフォーメーション(以下、DX)を推進します。
本計画では、DXを通じて、次世代を担う人材の育成と社会的課題の解決に貢献することを目指し、大学の教育・研究基盤のデジタル化を強力に推進します。さらに、デジタル技術を駆使した新しい看護教育モデルの構築に取り組み、看護分野におけるDXを先導します。
この取り組みにより、学生にはデジタル技術を活用した効果的な学びの場を提供し、教職員には教育・研究の質の向上を実現します。また、教育研究活動を通じて、地域社会との連携を深めることで、持続可能な社会の実現に貢献します。日本赤十字広島看護大学は、DX推進を教育の未来を切り開く鍵と位置づけ、その実現に向けて大学を挙げて取り組んでいきます。
本計画では、「日本赤十字学園 DX推進に関する基本方針」にある以下の5つの方針に従い、DX推進に取り組みます。これらの取り組みを通じて、本学は赤十字の理念に基づく看護教育の質をさらに高め、社会の変化に柔軟に対応できる看護専門職者の育成と、看護学の発展に寄与していきます。
- 教育の質の向上と学修成果の最大化のシナジー創出
- 学修環境の改善
- 学生・教職員の情報リテラシー向上とDX人材育成
- 研究環境の向上
- 大学運営の効率化
2. 基本方針(重点施策)
本学は、上記の目的を達成するため、学校法人日本赤十字学園のDX推進に関する基本方針に則り、次の方針に基づいてDX推進に取り組みます。各施策の実現時期は以下のように分類します。
- 短期目標:令和10年度(2028年度)まで短期
- 中期目標:令和15年度(2033年度)まで中期
- 長期目標:令和22年度(2040年度)まで長期
(1) 教育の質の向上と学修成果の最大化のシナジー創出
① 根拠に基づく看護実践能力の育成
ア 臨床現場で必要とされる専門知識・技術を効果的に伝えるために、デジタル技術を活用した教育の実践について検討します。具体的には、電子カルテや看護支援システムなどの操作演習、遠隔医療シミュレーションなどを通して、現場で使える実践的なスキルを育てます。長期
イ VR/AR技術を活用した、より実践的な看護技術の習得を支援するシステムの導入を検討します。例えば、VR空間上に患者の3Dモデルを構築し、様々な状況下における看護ケアを疑似体験できるシステムやシミュレーション人形と連携したVR/AR教材などのより実践に近い形で看護技術を習得できる導入を検討します。長期
② 個別最適化された学習支援
ア オンライン実習記録システムの導入により、実習記録の作成・提出・管理を効率化し、教員からの個別の学生に対するフィードバックを迅速化します。これにより、実習指導の質の向上と学生の学習効果の向上を図ります。短期
イ 学習分析機能を有した学習管理システム(LMS)の構築を進め、学生一人ひとりの学習履歴や理解度を分析できる仕組みを構築します。その分析結果に基づき、個別に最適化された学習指導、学習コンテンツの提供、学習進捗状況に合わせた助言などを行います。中期
ウ 学生が自律的かつ継続的に学べる環境を整えるため、AIを活用した24時間対応可能な学習支援体制の構築を目指します。時間や場所に制約されない柔軟なサポートを提供することで、学修の質と効果の向上を図ります。中期
③ 多様な学習ニーズへの対応
ア オンライン授業と対面授業を効果的に組み合わせたハイブリッド型学習環境を構築し、柔軟に学習スタイルを選択できる環境を提供します。短期
イ オンデマンド型のデジタル教材を充実させ、学生が時間や場所にとらわれずに学習できる環境を整備します。短期
ウ 遠隔授業システムの活用により、遠隔地の学生や社会人への学習機会を拡大します。短期
エ 講義映像や教材コンテンツの一元管理と配信、学生の視聴状況分析、質疑応答機能などを備えたコンテンツ管理システム(CMS)を導入します。これにより、教育コンテンツの体系的な管理、学生の主体的学習の促進、教員の負担軽減を図ります。短期
④ グローバル教育の強化
ア オンラインを活用した海外の看護大学との交流プログラムを拡充し、国際的な視野を持つ看護師の育成を強化します。長期
イ 英語での看護コミュニケーション能力を高めるためのオンライン学習プログラムの導入を検討します。中期
(2) 学修環境の改善
① キャンパスのスマート化
ア 学内Wi-Fi環境の整備・増強により、キャンパス内のどこでも快適にインターネットを利用できる環境を構築します。短期
イ 学生のPC端末必携化を推進し、学生が自身のデバイスを活用して学修できる環境を整備します。短期
② 学習スペースの多様化
ア ICT機器を活用したアクティブラーニングやグループワークに対応した講義室・実習室と学習スペースの整備・拡張について、具体的な検討を進めます。短期
イ オンライン学習用の個室ブースや、静かに集中してPC利用ができるスペースを整備・拡張について、具体的な検討を進めます。短期
③ デジタルツールの活用
ア 学習管理システム(LMS)やeポートフォリオシステムなどを活用し、学習成果を蓄積し、可視化します。中期
イ デジタルホワイトボードやタブレット端末などのICT機器を授業で活用し、双方向的な学びを実現します。短期
(3) 学生・教職員の情報リテラシー向上とDX人材育成
① 教職員の育成
ア デジタル技術を活用した教育手法や最新の看護学知見に対応できる教職員を育成するため、FD研修や情報共有の機会を充実させます。短期
② 学生支援の充実
ア 学生ポータルサイトを構築し、履修登録、成績確認、各種申請などをオンラインで完結できる環境を整備します。短期
イ オンライン学習環境やICT機器の利用方法に関するガイダンスを充実させ、学生のデジタルリテラシー向上を支援します。短期
ウ 学習支援システムやチャットボットなどを活用し、学生の疑問や相談に迅速に対応できる体制を構築します。中期
③ 生成AIの教育利用
ア 生成AIの教育利用に関するガイドラインを策定します。短期
イ 生成AIを活用した教材開発や個別学習支援など、教育の質向上に資する活用方法を検討します。中期
④ データサイエンス教育の導入
ア 看護実践におけるデータ分析手法の習得や、データに基づいた意思決定能力の育成を目指し、より充実したデータサイエンス教育を実施します。中期
⑤ 地域包括ケアを支える看護人材の育成
ア ICTを活用した多職種連携や、地域住民の健康管理・増進に貢献できる人材を育成します。中期
(4) 研究環境の向上
① 先進的な研究環境の整備
ア 研究データの収集・分析・管理を効率化するため、大学全体で利用可能なデータストレージを構築します。短期
イ 国立情報学研究所が提供する研究データ管理基盤であるNII RDC(NII Research Data Cloud)の導入と活用を進め、研究データのライフサイクル全体を効率的かつ安全に管理できる体制を構築します。短期
ウ 研究データポリシーを策定し、研究データの適切な取り扱いに関するルールを明確化します。短期
② 研究成果の発信力強化
ア 大学のウェブサイトや学術情報リポジトリをより充実させ、研究成果や論文を広く公開します。短期
イ 地域住民向けの公開講座やセミナーをオンラインで開催し、研究成果を地域社会に還元します。中期
③ 研究支援のデジタル化
ア 研究倫理審査申請のオンライン化など、研究支援業務のデジタル化を推進します。中期
イ 統計解析ソフトウェアを利用できる環境を整備します。中期
④ 共同研究の推進
ア オンライン会議システムやデータ共有プラットフォームを活用して行う海外の研究機関との共同研究を推進します。中期
イ 看護分野におけるDX技術の活用に関する研究を推進します。長期
⑤ リカレント教育の充実と生涯学習支援の強化
ア 地域の医療機関と連携し、ICT技術を活用して現場のニーズに応じたリカレント教育プログラムを開発します。短期
イ 現役の看護師や医療従事者向けに、最新の医療技術や知識を学ぶためのコースにオンライン講義を積極的に活用し、社会人にも学びやすい環境の構築を目指します。中期
ウ AI・IoTなどの最新技術を活用した医療や看護の動向に関する講座への参加を支援します。中期
エ リカレント教育プログラムの修了や特定のスキル習得に対して、学習成果の可視化と認定のため、オープンバッジシステムの導入を検討します。中期
オ 生涯学習プラットフォームを構築し、学習者同士や教員とのコミュニケーションを促進するコミュニティ機能を実装します。長期
カ AIを活用したレコメンデーション機能を導入し、各学習者に最適な学習コンテンツやプログラムを提案します。長期
(5) 大学運営の効率化
① 業務プロセス改革
ア 人事システムと会計システムなどの業務システムを統合し、業務の効率化と情報共有の促進を図ります。中期
イ AI技術と既存のRPA(Robotic Process Automation)を組み合わせて、定型業務の自動化を図ります。中期
ウ 最新のAI技術を情報の安全性に配慮する形で取り入れ、業務効率の改善を目指します。中期
② 手続きのオンライン化・ペーパーレス化
ア 各種手続きのオンライン化を段階的に進め、学生・教職員の利便性向上と事務処理の効率化を図ります。具体的には、入学手続き、履修登録、各種証明書発行、休暇申請などを優先的にオンライン化し、24時間365日どこからでもアクセス可能なシステムを構築します。短期
イ 会議や研修のオンライン化を推進することで、移動時間やコストの削減を図ります。対面での実施が必要な場合とオンラインで実施可能な場合を明確に区分し、ハイブリッド型の会議・研修システムを導入します。これにより、遠隔地からの参加も容易になり、より多様な意見交換や学習機会の創出が可能となります。短期
ウ 授業や会議における紙での資料準備を段階的に廃止し、完全なペーパーレス化を目指します。そのために必要なデバイス(タブレットやデジタルホワイトボードなど)の導入と、教職員向けの利用研修を計画的に実施します。同時に、デジタルならではの利点(資料の即時更新、マルチメディア活用など)を最大限に活かせるよう、コンテンツ作成のガイドラインを策定します。短期
エ クラウドベースの文書管理システムを導入し、電子データでの保存を推進します。これにより、文書の検索性向上、版管理の徹底、情報共有の円滑化を実現します。また、文書の重要度に応じたアクセス権限の設定や、暗号化などのセキュリティ対策を講じ、情報の機密性を確保します。さらに、電子署名の導入により、契約文書等の電子化にも対応します。短期
③ クラウドコンピューティングの積極的な活用
ア 低コストでありながらセキュリティとスケーラビリティを兼ね備えたシステムを構築するために、ハイブリッドクラウドを基盤としつつも、クラウドサービスを積極的に採用していきます。クラウドサービスの導入に際しては、情報セキュリティや個人情報保護の観点から法的制限を十分に考慮し、コンプライアンスを徹底します。また、システム運用に係るコストの最適化を図り、持続可能な運用を実現します。さらに、クラウド技術の進展に伴い、最新の技術を取り入れることで、より高度なサービス提供を目指します。中期
④ データに基づく大学運営
ア 財務状況の可視化と情報公開を推進し、ステークホルダーに対する説明責任を果たします。短期
イ 大学運営に関わる各種データを収集・分析し、経営戦略や意思決定に活用する「IR (Institutional Research)」を推進します。分析結果はBIツールなどを利用して学内に情報を提供し、学内の意思決定のシーンにおいて、いつでもどこでも、最新のデータをもとにした意思決定ができる環境の構築を目指します。中期
ウ データ分析に基づいた戦略的意思決定を推進します。デジタルマーケティングの手法を活用した戦略的な広報活動を展開し、志願者獲得やブランド力向上を図ります。中期
3. 推進体制
本計画の推進にあたっては、「経営会議」を中心とし、全体的な方針決定と進捗管理を行います。具体的な施策の立案と実行については、以下の体制で進めていきます。
(1) 経営会議
- DX推進計画の全体方針の決定
- 重点施策の承認
- 進捗状況の評価と計画の見直し
(2) DX推進チーム
- 経営会議の下に設置
- DX推進計画の具体的な実行計画の策定
- 各委員会・部署間での調整と連携促進
- 各委員会・部署からの進捗報告の取りまとめ、経営会議への報告
- 評価を踏まえた計画の見直しや新たな方針の策定の提案
(3) 各委員会・部署
- それぞれの活動内容に応じた具体的施策の検討と提案
- 担当分野におけるDX推進施策の実行
- 定期的な進捗報告とフィードバックの収集・評価
(4) DX推進担当者
- 各部署に1名以上配置
- 部署内でのDX推進施策の推進と調整
- DX推進チームとの連絡窓口
この体制により、経営会議による全体方針の決定と、各委員会・部署による具体的施策の立案・実行を両立させます。DX推進チームが全体の調整を行い、各部署のDX推進担当者が現場レベルでの実践を担当することで、組織全体でDX推進に取り組む体制を構築します。
4. 評価と見直し
各施策の進捗に加えて、教育や研究の質向上に対する効果や施策自体の有効性についても、学修者の視点に立って総合的に検証・評価し、改善に向けた検討を継続的に行います。
また、社会情勢や技術動向の変化を踏まえながら、実施状況を柔軟に見直し、必要に応じて内容の再構成や方向性の転換も視野に入れた対応を図ります。
5. リスク管理とセキュリティ対策
DX推進に伴い情報セキュリティリスクが高まることを認識し、以下の対策を講じます。
(1) 情報セキュリティポリシーの見直しと強化
最新の脅威に対応できるよう、情報セキュリティポリシーを定期的に見直し、強化します。
(2) 教職員向けの情報セキュリティ教育の実施
全教職員を対象に、情報セキュリティに関する定期的な教育・研修を実施し、意識向上を図ります。
(3) 定期的なセキュリティ監査の実施
外部専門機関によるセキュリティ監査を定期的に実施し、システムの脆弱性や対策の不備を洗い出し、改善します。
(4) インシデント対応計画の策定と訓練の実施
情報漏洩等のインシデント発生に備え、対応計画を策定し、定期的な訓練を実施します。
6. 財源確保と投資計画
DX推進に必要な財源を確保するため、以下の取り組みを行います。
(1) 補助金や助成金の積極的な活用
国や地方自治体、関連団体等が提供する補助金や助成金を積極的に活用します。
(2) 産学連携による外部資金の獲得
企業や研究機関との共同研究、受託研究などを推進し、外部資金を獲得します。
また、中長期的な視野を持った検討に基づき、計画的なDX投資を行います。その際、各施策の導入・運用にかかるコストと、それによって得られる効果(業務効率化、教育・研究の質の向上、学生募集力の強化など)を総合的に評価するコストベネフィット分析を行い、費用対効果の高い施策を優先的に実施します。投資効果の継続的なモニタリングと評価を通じて、DX投資の最適化を図ります。
おわりに
このDX推進計画の実施により、本学は教育・研究・運営のあらゆる面でデジタル技術を活用し、社会の変化に柔軟に対応できる体制を構築します。
これにより、本学の強みである赤十字の理念に基づく看護教育の質をさらに高め、「命と尊厳を守るヒューマンケアリングの実践者」として社会に貢献できる人材の育成と、看護学の発展に寄与していきます。全教職員が一丸となって本計画に取り組み、本学の更なる発展を目指します。
短期アクション[令和10年度(2028年度)まで]
本計画における短期アクションは、DX推進の基盤整備と即効性のある事業を中心に実施します。学生・教職員が早期にDXの効果を実感できる施策を優先的に推進します。