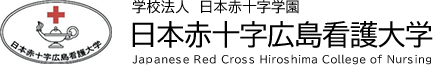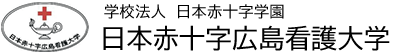本文
令和5年度 外部有識者会議
本学が、学校運営の改善や教育活動の質向上を恒常的に進めていくため、令和2年度から地域や産業界、学校関係者等の学外の有識者をお招きし、客観的な視点からのご意見を伺う会議を設置しており、今年度は8月31日に開催しました。
○会議の方法と構成
次の委員の方が、本学学長(及び関係教職員)との間で質疑や意見交換を行います。
・国立大学法人広島大学 広島大学病院 副病院長(兼)看護部長
・廿日市市 健康福祉部長
・地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院 副院長(兼)看護部長
・広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院 副院長(兼)看護部長
・学校法人甲南女子学園 甲南女子大学 看護リハビリテーション学部長
・公益社団法人 広島県看護協会 会長
○令和5年度会議の概要(令和5年8月31日開催)
大学から、(1)大学の現況、(2)・令和5年度本学の取り組みについて ・今後のシミュレーション教育の充実に向けた計画について ・看護の基盤実習Ⅰの結果について説明し、それを踏まえて質疑や意見交換を行いました。
【質疑・意見交換の概要】
(意見)シミュレーション教育の充実のために模擬患者を活用しているとのことだが、目的と養成の仕方を教えてもらいたい。
(回答)地域住民からボランティアを募り、月に1回、6カ月かけて学内で訓練を受けてもらっている。模擬患者とは何かから始まり、病気への理解を進めてもらい、特に心の動きを表現する演技のトレーニングに時間をかけている。年齢層も50代から80代と幅広く、現在、約30名登録があり、年間200件ほど協力してもらっている。モデル人形にはできない患者役になりきってもらうことで、実践的な教育となり、学生にとって看護技術のフィードバックを得ることができる。また、模擬患者のみなさんにとっても、自身の健康を考えてもらう機会となっている。
(意見)地域の方が参加して、人の役に立つ活動をしているのは非常に素晴らしい思う。この取り組みをもっと発信していけたらよいのではないか。
(意見)臨床現場において様々なシチュエーションがあり、患者から意図せず厳しい発言を受ける時がある。そうしたことに対応するシミュレーション教育などは行っているか。
ちなみに臨床現場でも、そのような場面での対応について模擬の研修に力入れている。
(回答)模擬患者に認知症患者の役になってもらい、帰宅願望があり、大声をあげたり危険な行動をとろうとしたりした場合の対応を想定したシミュレーションはある。ただ、どうしても模擬患者が学生に対して遠慮してしまい、控えめな行動になる場合がある。学生のために、模擬であっても生身の患者として、より現実の現場に則した内容に高めていきたい。
(意見)基礎教育実習はいずれの大学も力を入れているが、貴学では模擬患者育成の中に心の動きを取り入れ、学生への教育に思いが伝わる内容だと思った。
(意見)18歳人口が減っていく中、これから大学の魅力、特に貴学の特色であるヒューマンケアリングをどのように伝えていきたいと考えているか。
(回答)全国の私立大学の中には受験者数が減少して、定員の充足率が5割を割るところもある。本学は今は定員を満たしているが、これからはいかに看護に関心を持ってもらい、受験動機となるまで魅力を伝えていくかが課題となってくる。このため、ヒューマンケアリングの理念や様々な活動をホームページで掲載しているほか、学生自身が「ぴーあーるLABO」という広報チームを作り、ブログやInstagramなどに投稿して情報を発信している。また、大学での教育だけでなく、赤十字の強みで実習先、就職先とも連携していることを意識して発信しており、看護師を目指す方にこの点をアピールしていきたい。
(意見)入学試験について、赤十字特別推薦の募集人数が10名程度に対し、出願数が毎年1名なのはなぜか。
(回答)令和3年度よりJRC(※1)活動をしている生徒を対象に導入した制度であるが、日が浅く周知されていない。また、JRC活動をしている生徒がみな看護師を志望しているわけではないので、看護職に興味を持ってもらうためのさらなる広報が必要と考えている。
(意見)福祉の大学で学んでも就職先が福祉現場ではなく、現場に職員が集まらないと聞く。看護の現場でも人材確保は課題だと感じている。
(意見)先ほどの意見同様に急性期病院においても2040年問題(※2)を控え、また教育でも地域包括ケアを学ぶためか人材確保は課題となっている。関東圏でも新卒の看護師が急性期病院を回避し、人材確保が困難な状況になってきていると聞くが、貴学でも学生の傾向が変わってきているように感じるか。
(回答)地域のことを学ぶのは急性期病院を退院後の患者像を知るためで、本学においては、やはり急性期病院を志望する学生のほうが多い。しかし、赤十字病院の奨学金を受けながらもそれ以外へ就職する場合もあり、学生の考え方が多様化していると感じている。
(意見)毎年5月12日の看護の日に合わせ、これからの看護の担い手となる小中高の児童・生徒に、看護職を選択してもらえるような学習体験ができるイベントなどを実施したいので、大学でも良いアイデアがあれば提供して頂きたい。
(回答)本学でも、小学校などに赴きプレゼンテーションなどを実施したい。このような活動は重要であり、大学教育だけでなく全体的な事でもあるので、各方面の協力を得ながら発信していきたい。
現在は社会の変化が早く過渡期とも言える時代であり、大学としても様々な流れに遅れないように取り組んでいきたい。
※1 JRC…Junior Red Cross青少年赤十字・日常生活の中での実践活動を通じて地域社会への貢献や世界のために奉仕し友好親善の精神を育成することを目的とした団体
※2 2040年問題…少子化による人口減少と高齢者人口がピークに達することで直面すると考えられる問題の総称