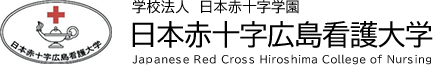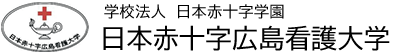本文
令和4年度第1回 外部有識者会議
本学が、学校運営の改善や教育活動の質向上を恒常的に進めていくため、令和2年度から地域や産業界、学校関係者等の学外の有識者をお招きし、客観的な視点からのご意見を伺う会議を設置しており、今年度は6月21日に第1回会議を開催しました。
○会議の方法と構成
次の委員の方が、本学学長(及び関係教職員)との間で意見交換を行います。
・国立大学法人広島大学病院 副病院長(兼)看護部長
・廿日市市 健康福祉部長
・地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院 副院長(兼)看護部長
・広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院 看護部長
・学校法人甲南女子学園甲南女子大学 看護リハビリテーション学部長(兼)大学院看護学研究科委員長
・公益社団法人 広島県看護協会 会長
○令和4年度第1回会議の概要(令和4年6月21日開催)
大学から、(1)大学の現況、(2)令和4年度本学の新たな取り組み(・新カリキュラムの実施(カリキュラムポリシー)について ・臨床教授等の称号付与について ・教員組織の編成及び運用について)について説明し、それを踏まえて質疑や意見交換を行いました。
【質疑・意見交換の概要】
(意見)学生支援にチューター制度が導入されているが、担当する学生の人数、学習指導や生活支援の具体的な内容は。
(回答)教員1名あたり15人程度の学生を担当し、講義の履修登録時の相談や成績、模試の結果等について面談を行い、予習・復習の実施状況を踏まえた学習指導をしている。また、大学入学を機に1人暮しを始める学生も多く、日々の生活相談や指導、就職支援等の生活支援をしている。なお、チューターは1年交代であり、次のチューターに引き継ぐためのツール(チューターカード)を準備し対応している。
(意見)CAP制(※1)を継続して導入しているが、新カリキュラムになって履修登録できる単位数の上限は変更となったか。
(回答)履修登録できる単位数の上限は昨年度から変更はない。GPA(※2)の高い学生は追加で単位を取得することは可能だが、実習もあり必修科目自体が多いため、CAP制の単位数を超えて取得する学生はほぼいない。
(意見)病院に体験学習に来た高校生から、看護師になるために「どこの大学に進学すればよいか」、「専門学校との違いは何か」等の質問があった。貴学における特徴や進学した際のメリット、入学希望者へのアピールポイントは何か。
(回答)少子化のなか、本学の特徴を明確にすることが課題となっている。これまではヒューマンケアリングの実践者と看護現場での実践力を特徴とし、OSCE(※3)、CBT(※4)、演習を積み上げて実践力の強化を行い、現在、eポートフォリオ(※5)評価の導入を検討している。また、赤十字の大学として、国際救援・開発協力看護師コースや災害看護も強みであり、これらも加え、本学の特徴としてアピールしていきたい。
(意見)在宅での生活者が増える中で、専門性を高めながら多職種との連携が必須となるが、新カリキュラムでは1年時に「多職種連携論」が新たに位置づけられ、看護の基盤実習1で「地域で生活する人々の健康」が掲げられることで、高齢者等の地域での生活をイメージできる学問となり、総合的に学修できるカリキュラムとなっていると評価できる。
(意見)認知症サポーター養成講座に貴学の学生に参加してもらっているが、講座で知識として得たことに加え、家族や当事者との関わりを感じることができるサロンへの参加、実際のサポーターとして活動する場を提供できれば、更に体感して身に付くのではないか。
(回答)新カリキュラムの看護の基盤実習1では、地域のサロン、診療所、小学校、地区踏査に全員がそれぞれ1日参加し、小学校では養護教員から発達段階に合わせた子どもの健康管理の話を聞く等、生活をしている人の視点に立ち実習にて総合的な学修を行うこととしている。
(意見)前回の会議で提案した病院での学生によるボランティア活動について、さっそく参加してもらったところ院内の看護師から好評であった。
(意見)認定看護師教育課程(摂食・嚥下看護師)は、今年度から3年間休講としているが、今後の方向性は。
(回答)昨年度の同教育課程の入学者は定員の半数(15名)であった。また、休講の告知後も問合せ件数は5件にも満たない状況であること、広島県内を含め、中国・四国9県内の認定看護師の充足率は全国と比較し高いこと、B課程へのシフト等制度や現場の看護師の志向の変化もあり今後も定員に満たないことが予測されること等から、3年間の休講期間を待たず、今年度末で閉講する方向で学内の検討を進めている。
(意見)学生の就職率や国家試験等の合格率を事業評価とする大学が多い中で、貴学では結果だけでなく、そこまでに至ったプロセスを重視した事業評価をしている点は良い。
(意見)一般的に授業評価から授業内容の見直し・改善は教員が主として行っているが、貴学では教員に加えて授業を受けた学生と共に授業評価や内容を話し合うような取り組みはされているか。大学の教育をよくしようと考えると教員主体になりがちであるが、学生の意見からしか教育をよくする手段はないのではないかとも思われるため、取り組まれていれば教えてもらいたい。
(回答)学生はアンケートにより授業評価を実施し、教員はこれに対するコメントを公開しているのみで、学生と授業評価を話し合うまでには至っていない。今後、学生を巻き込んだ取り組みを検討してみたい。
(意見)卒業生と大学との関係性について、大学のPRや卒業生の大学での役割を教えてもらいたい。
(回答)卒業生には、キャリアガイダンスで在校生に就職のアドバイスをしてもらっている。また、今年度はホームカミングデーを3回開催する予定で、教員との交流を深め大学院への進学にも繋げたいと考えている。ただ、卒業生との連携は本学の弱いところであり、卒業生との連絡体制が十分に整備されてない。なお本学には同窓会への入会者が少なく同窓生が交流する機会がない状態である。
(意見)学生の学修成果の把握として、「予習しない学生を20%以下」としているが、数値の根拠や昨年度との比較はどうなっているか。
(回答)チューターから学生へ1週間の学修時間を確認し、予習をしていない学生を減らしていくように指導しており、(目標数値に拘らず)学生全体の学修時間の底上げを取組方針としている。
(意見)臨床指導者研修会の定員30名は、貴学の臨地実習の受入施設数か。
(回答)臨地実習の受入施設を主な対象としており、本学のカリキュラムや目的等も伝えて実習指導の充実を図っていただくことが目的である。なお、修了者には本学の認定証を発行している。
(意見)臨床現場の看護師から相談を受けることがあるが、限界や行き詰まりを感じている人には、貴学の大学院を勧めることがある。広島に貴学大学院がある意義は大きいので、紹介等でさらに連携していければよい。
(意見)アクティブラーニングはどのように行っているか。
(回答)アクティブラーニングは何年も前から大学教育に必要とされ、それぞれの科目で取り組んでいる。看護学部は演習が多くアクティブラーニングに準じた授業を行っているが、更に発展させ反転授業とまではいかないが、事前課題を与えグループディスカッションを行いまとめるといった流れを基礎看護学等で行っている。またGoogle Formsで学生に設問を与え、回答の集計結果を基に講義する場合もある。アクティブラーニングでは、教員からの一方通行とならず双方向性で、いろいろなツールを活用しつつ学生が自らの育ちを感じ自己統制力等の成果を出す機会となることが重要である。
(意見)IR推進委員会で評価・分析をされているが、教育の質を上げるためにどのような取り組みをしているか。
(回答)IR(※6)は、データの選択や分析方法等が非常に難しい。IR推進委員会で準備をしてきたが、教育の質を上げるため何をどのように分析・評価するかの具体的な検討は、今年度から進めていく予定である。
(意見)教育教材におけるDX(※7)やVRの推進についてはどのように取り組まれているか。
(回答)DXについては、特にアバターを含めてVRを推進する必要があると認識しており、本学の看護教育開発委員会でバーチャルを含めた様々な教材を集め、導入の検討をしている。
※1 CAP制…単位の過剰登録を防ぐため、1年間あるいは、1学期間に履修登録できる単位の上限を設ける制度。
※2 GPA…Grade Point Averageの略。各科目の成績から特定の方式によって算出された学生の成績評価値のこと。
※3 OSCE…Objective Structured Clinical Examinationの略。臨地実習に進む前に、一般診療に関する基本的臨床能力を備えているかの評価を行う客観的臨床能力の実技試験。
※4 CBT…Computer Based Testingの略。コンピュータを使った試験方式。臨地実習前にテストを行い、臨地実習に向けた学習に役立つよう実習に即した内容を出題し、学生の主体的な取り組みを促進する。
※5 eポートフォリオ…学修過程や各種の学修成果をインターネット上に長期にわたって収集し、記録したもの。
※6 IR…Institutional Researchの略。機関の計画策定、意思決定を支援するような情報を提供すること。特に学生の学修成果など教育機能についての調査分析、大学経営の基礎となる情報の分析を行い、またそれらの分析結果の提供を通じて大学の自己評価、意思決定に寄与する活動。
※7 DX…Digital transformationの略。教育分野においては、個別データを保存したうえで個別学習や生涯にわたる学習を最適化したり、医療・福祉など他分野のデータと相互連携したりするなど、データ連動により学習モデルの構造が変革し、新たな価値が創出されるもの。