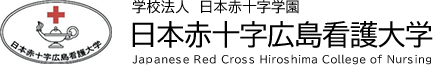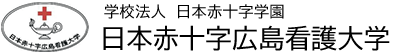本文
令和3年度第2回 外部有識者会議
本学が、学校運営の改善や教育活動の質向上を恒常的に進めていくため、昨年度から、地域や産業界等の学外の有識者をお招きし、客観的な視点からのご意見を伺う会議を設置しており、今年度は5月の第1回に引き続き第2回会議を令和4年1月19日に開催しました(参集+Web)。
○会議の方法と構成
次の委員の方が、本学学長(及び関係教職員)との間で意見交換を行います。
・国立大学法人広島大学病院 副病院長(兼)看護部長
・廿日市市福祉保健部長(兼)福祉事務所長
・地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院 副病院長(兼)看護部長
・広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 看護部長
・公益社団法人広島県看護協会 会長
○令和3年度第2回会議の概要
本学から
1 財団法人大学基準協会大学評価申請の点検・評価報告書(案)について
2 本学における今後の看護師継続教育について
3 学修成果情報(ディプロマサプリメント)の検討状況について
4 大学院履修証明プログラムについて
現況や課題を説明し、それを踏まえて質疑や意見交換を行いました。
【質疑・意見交換の概要】
●点検・評価報告書(案)について
(意見)内部質保証について、組織横断的な質保証委員会の構成と議論内容は。
(回答)教授会メンバー及び事務局職員にて構成している。
(意見)コロナ禍でDX(※1)が推進されていると思うが、貴学の教育ではどう進めているか。
(回答)IR推進委員会を設け、学内にある様々なデータを分析し、結果をPDCAサイクルで活用して教育の質向上に反映するように取り組んでいる。また、DXプロジェクトを立ち上げ、VRをどのように教育に取り入れるか検討しているほか、臨床推論を強化するための学内演習とその評価をどのようにするか検討しているところである。
(意見)学生支援について、正課外活動特にボランティア活動が活かされているか。
(回答)ボランティア活動は、社会福祉協議会からの紹介で、例えばごみ屋敷の整理や、教員の豪雨災害ボランティアセンター支援に随行しての活動などである。また今年度は、ワクチン集団接種会場で、受診者や従事者を支援するアルバイトもしている。学生は社会経験が乏しいところがあるので、ボランティア活動は社会を知る良い機会と捉えている。また、災害関係は防災意識を高めるうえでも有益であるし、赤十字の基本である人道の精神を育むうえでも強みとなると考えている。
(意見)地域住民への研修会や教育研究成果の還元についての記述に「若年層への発信不足」とあるが、幅広い年齢層への活動については。
(回答)助産学の授業では、特別支援学校や小中学校への「いのちの授業」などを行っている。防災関連では、早稲田大学、和歌山県湯浅町との学校防災教育の連携プロジェクトを、廿日市市と広げていく。まずは小学校での防災意識に関するアンケート調査に着手している。また、来年度からの新カリキュラムでは、1年生での実習で、医療機関ではなく地域に出て健康問題を考える授業を計画している。
(意見)こどもへの教育は(家庭内など)大人への拡散が期待できるため、ぜひ進めていただきたい。
(意見)病院にボランティアを申し出る看護学生がいるが、患者との触れ合いができる。コロナが落ち着いたら、貴学からも臨床の現場にぜひ来てほしい。
(回答)本学でもどういった場所に課外活動・ボランティアに行けるか検討している。また、情報の窓口の一元化を行う予定であり、ヒューマンケアリングセンターをその窓口にしたいと考えている。
(意見)学生支援についての問題点として学生の自主性の低下を挙げているが、コロナ禍も1年経過したなかで、学生も変わってきて積極的になったと現場から聞いている。
(回答)学生支援はチューター制をとっており、教員1名あたり15人程度とし、きめ細やかな学習のサポートを実施している。待ちの姿勢が見られることについては学生の問題だけではなく教員側の問題もあると認識しており、FD(※2)などを実施して改善に努めている。
(回答)1週間や2日だけでも臨地実習に行けるなら行きたいという学生が多い。臨地しか学べないことがあり、これまで行けなかった反動、臨地で学べない危機感から積極的に質問する学生が多かったと受入先からも聞いているので、さらに活かしたい。
(意見)大学運営の項で「2040年に向けたグランドデザイン」の記述があるが、どのように対応していくのか。
(回答)グランドデザインや将来構想は、学園全体の大きな方針がないといけない。日本赤十字学園が設置している6大学の赤十字の強みを生かし、一方で少子化や看護職の需要等がどうなるかなどを見通して考えていく必要があると認識している。来年度、学園全体として議論し、それを受けて本学としても検討したい。
(意見)財務の項で「決算の黒字確保以外の目標設定をしていない」とあるが、これ以外にどのような目標が考えられるのか。また、管理経費比率は、全国平均8.9%に対し4.2%とかなり低いが、何が要因か。
(回答)例えばであるが、学生納付金比率が全国平均より高いので授業料以外の収入を増やす、寄付金比率が低いので増やす、また将来の施設設備の更新に備える積立金への組み入れを確保するなどがあり、検討したい。管理委託経費は、本学は小規模であり業務を委託ではなく直接実施する、学生募集に他の私立学校ほどは経費をかけていないなどが考えられる。
(意見)前回の会議で臨床教育の教員について他施設との人事交流が議論されたが、現状はどうか。
(回答)現時点では具体的に決まったものはないが、推進に向け検討していきたい。
●看護継続教育について
(意見)臨床指導者研修会の内容について、県委託で県看護協会が実施している講習会とは異なるメニュー(リフレクション等)があり、時間的にも参加しやすく良いと思う。連携してPRしていければよいのではないか。
(意見)臨床としては大変ありがたく、ぜひ参加させたい。
(意見)認定看護師教育課程を休講するとのことだが、今後、特定行為を組み込んだ課程での開講はないのか。
(回答)本学としてはその意向はない。大学院の修士課程にCNS(※3)4コースを設けているが、希望者が少ない現状であり、高度実践化をどこまで進めるか、2040年を見据えて考えていきたい。
●ディプロマサプリメントについて
(意見)こういった取り組みは、看護師を採用する側としてはありがたい。推薦書なども見るが、学生それぞれの背景が分かりにくい。面談の時間が短いなかで本人としては伝えきれない様子のこともあるが、これは本人からの情報も多くあり、有用と考える。
(意見)成績以外の多くは自己評価であるが、客観的評価を入れないのか。
(回答)全ての評価項目について、特にコアコンピテンシーなどは教員が確認し評価するのは難しいが、教員とやりとりしながら自己評価しているので、一定の客観性はあると考えている。
(意見)ディプロマサプリメントは全国的なものか。
(意見)近年出てきたもので、日赤看護大学では九州に続き2カ所目。総合大学は取り組んでいるところがあるが、まだ全国的ではない。
●大学院履修プログラムについて
(意見)当院にも研究手法を学びたい、あるいは進学を希望する看護師はいるが、家庭の問題や学費の問題があり苦慮している。
(意見)当院では、計画的に履修させている。一方で、修了生を核に来年度から看護研究ワーキングチームをつくり、内部で看護研究の推進に取り組みたい。
(意見)貴学の取組を知って、学びを止めない継続教育の重要性を再認識した。
以上
※1 DX…デジタル・トランスフォーメーションの略で、教育分野においては、個別データを保存したうえで個別学習や生涯にわたる学習を最適化したり、医療・福祉など他分野のデータと相互連携したりするなど、データ連動により学習モデルの構造が変革し、新たな価値が創出されるもの。(文部科学省大臣官房文部科学戦略官・総合教育政策局教育DX推進室長の桐生崇氏発言より)
※2 FD…ファカルティ・ディベロップメントの略で、教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取組の総称 。(中央教育審議会指針 用語集より)
※3 CNS…専門看護師(Certified Nurse Specialist)の別称で、複雑で解決困難な看護問題を持つ個人、家族及び集団に対して水準の高い看護ケアを効率よく提供するための、特定の専門看護分野の知識及び技術を深めた看護師で、日本看護協会専門看護師認定審査に合格し、ある特定の専門看護分野において卓越した看護実践能力を有することが認められた者のことをいう。(日本看護協会ホームページより)