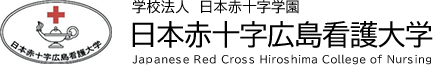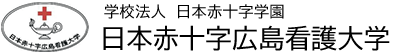本文
令和2年度 外部有識者会議
本学が、学校運営の改善や教育活動の質向上を恒常的に進めていくため、このほど、地域や産業界等の学外の有識者をお招きし、客観的な視点からのご意見を伺う会議を設置し、その第1回会議を10月30日に開催しました。
会議においていただきましたご意見は今後の本学の取組の参考として活用するとともに、今後も毎年度、定期開催して、状況変化等を報告するとともに、様々なご意見をお聞きしていく予定です。
○会議の方法と構成
次の委員の方が、本学学長(及び関係教職員)との間で質疑や意見交換を行います。
・国立大学法人広島大学病院 副病院長(兼)看護部長
・廿日市市 福祉保健部長(兼)福祉事務所長
・地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院 副病院長(兼)看護部長
・広島県厚生農業協同組合連合会広島総合病院 看護部長
・公益社団法人 広島県看護協会 会長
○第1回会議の概要(令和2年10月30日開催)
大学から、(1)大学の現況、内部質保証システム等について、(2)3つの方針(卒業・修了認定・学位授与、教育課程の編成、入学者受入)と方針を踏まえた本学の取組みについて、(3)学修成果情報(ディプロマサプリメント)について、現況や課題を説明し、それを踏まえて質疑や意見交換を行いました。
【主なご意見】
(1) 3つの方針(学部・大学院)に係る評価について
・ディプロマポリシーは、赤十字の理念である、ヒューマンケアリングや国際救援・開発協力看護師コースについて記載してあり、赤十字の看護大学としての特徴が理解できる。
・赤十字病院の看護師による指導(RCNES)や模擬患者(SP)養成による演習への活用は、コミュニケーション能力の育成やメンタル強化にも役に立つので、積極的に進めていただきたい。
・アドミッションポリシーに関して、高大接続の一環として行っている、入学決定後の課題提示とレポート提出は有用であり、フィードバックの方法について引き続き検討していただきたい。
・地域包括ケア時代に向けたカリキュラムの改正検討は、医療施設でも地域に何を期待され、どう貢献していくかが課題となっているので、地域と連携できるよう検討していただきたい。
・実習では、活発に討議ができるグループと個の話題に留まるグループなど、差があり、グループによるダイナミクスが引き出せていない事例がある。
(2) 本学の学修成果に関する情報提供の内容及び方法について
・ディプロマサプリメントは、採用側には有効な情報である。正課外の活動状況は、その目的等を面接で必ず確認して選考している。
・ボランティアやアルバイトは忍耐力やコミュニケーション能力が醸成でき、新人教育の参考にもなる。
(3) 本学卒業生の就職後の資質・能力について
・毎年、受け入れているが、年度で学生のカラーが違うと思う。受け入れ側としては、大学でどういう特色を持って育ててきたかがわかれば、採用後の新人教育に活かすことができる。
・大学卒も専門学校卒も、メンタル面の強さが求められるのは同じ。社会性が求められるので、赤十字の大学として、基礎教育の充実と、学生の社会性、社会的スキル向上に努めていただきたい。
(4) 本学が取り組んでいる地域との連携方策・事業について
・地域共生型社会の構築に向けて、自治体との包括連携協定に基づく活動の強化を検討されたい。
(5) その他
・臨床における指導力強化には、現場サイドでもスキルを身につけたいとの希望があり、本学でも実施すればモチベーションも上がるし機会の拡大になる。